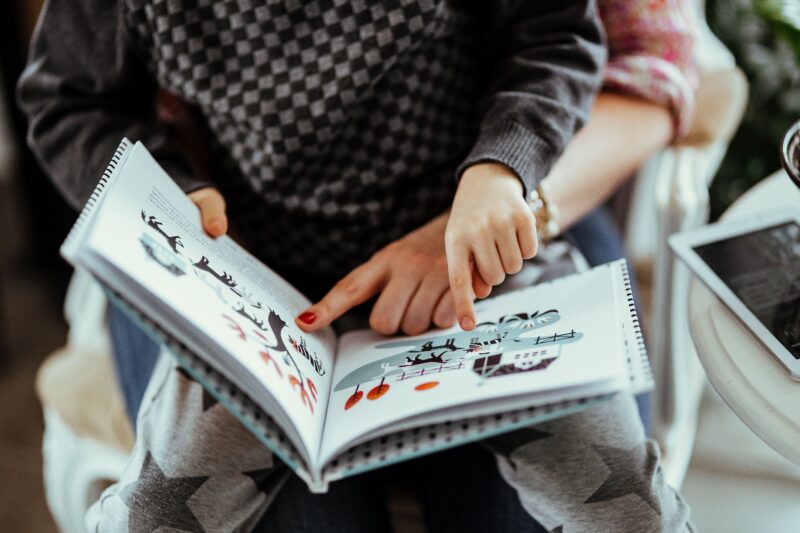
「ホームスクーリングをはじめる前に重要なこと」でも書きましたが、「生きてていいんだ」「がんばるといい事があるかもしれない」など自分を受け入れる自己肯定感、自分がやると何かしら効果がでる自己効力感がこれからの時代を生きていく上で大切です。これらは健康に元気に生きていて、自己肯定感や自己効力感は意識しなくても備わっている人は意識する必要はありません。ですが学校に行けなくなって落ち込んでいる子ども、自分はがんばっているのに理解されていないと感じている子どもに対しては意識的に育みたいものです。
家にいて行動機会が少ない子どもにとって、自己肯定感・自己効力感を育む機会も少なくなります。家で少しずつ親や家族の声かけで育てていけると良いと思います。
声かけのポイント
① 何かやった/できた時に伝えるのではなく、やりはじめた時にまず伝える(スモールステップ)
② 大げさに褒めない(大げさに褒めてもいいけど、あまりしょっちゅうしない)、端的にできていることを伝える
③ 質より量、回数が多い方がいいでしょう
④ 褒めた後の子どもの反応を観察する。どんな褒め方が刺さるのかをチェックする
できれば褒めたことや反応を(全部じゃなくても)記録できるとなお良いのですが、私自身もあまりできていないので、親自身も完璧を目指さず、「お、これはいい褒め方だった/いい感じの反応だった」という事は記録に残しておくようにしましょう。今はスマホだと音声入力もできますし、本当に簡単にメモ機能に残すでもOKです。
赤ちゃんの時によく活用した、おしっこやうんちの記録である「赤ちゃん日記」のようなものを再度つけていくイメージです。「勉強にとりかかった」などのケースは褒めるタイミングとして理想ですが、本を読み始める、あるいはそれも難しい子はまず衣食住から「夕食を食べられた」でもいいでしょう。食事の場合はご家族が作ることも多いので、「食べたね」という声かけのほかに「食べてくれてうれしい」というIメッセージ(アイメッセージ)を入れたりすると効果的です。またお手伝いをしてくれたときに「やったね」というほかに、「やってくれて助かる」「ありがとう」などさらりと付け足すとより効果的です。
声かけは本当に簡単で、すぐ終わり、誰でもできます。ただし、声のかけ方には工夫が必要です。お子さんに合わせて試行錯誤しつつ、量をこなして自己肯定感を上げていきましょう。声をかけている親御さん自身を労わることも忘れずに。
-

- 保田典子
筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。
