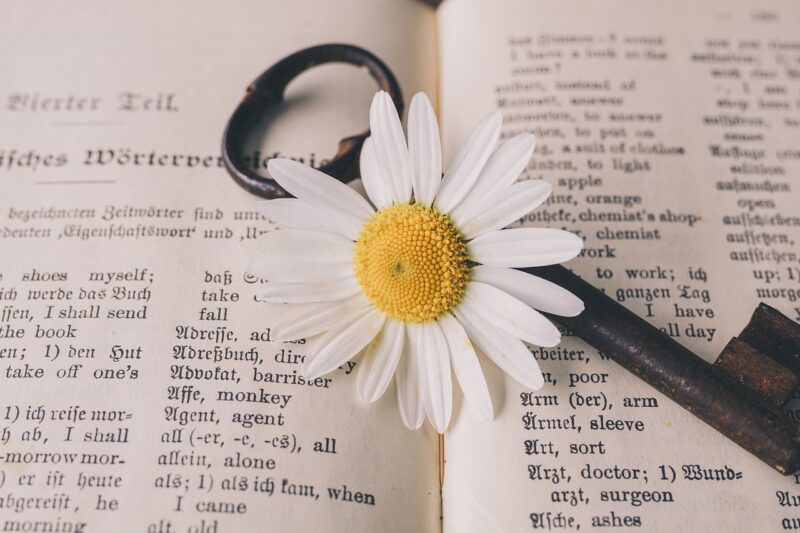
1歳前半から2歳、場合によっては3歳頃のお子さんを持つ親御さんから、「言葉が出ない」という相談をうけることが多々あります。この年齢の子どもたちは言葉の発達に大きな個人差があるため、親御さんたちが不安を抱えるのも無理はありません。ただ診察・観察を行っても、重度の障害がない限り知的障害を伴っているのかを明確に判断することは難しいです。経験豊富な専門家からであればより深い洞察を得ることもありえますが、それでもはっきりとした結論を得るのには時間がかかります。
数年後に振り返ってみると「結局、発達は正常だった」「発達障害があった」「知的障害も合併していた」というように特性が明確になるケースが多いです。しかし、親や周囲の大人が気になるのは、現在の状況に対してどう対応すればよいのかということ。様子を見て終わらせるのではなく、できることを考えて行動することが重要になります。
言葉の発達を支えるためにできること
言葉はコミュニケーション手段です。コミュニケーションをとりたいという気持ちが強くなることで、言葉が出やすくなると言われています。そのためには、人に対する関心を高めることが大切です。具体的なアプローチとしては、以下のような方法があります。
自分の世界に関心を示す
言葉が出ない子どもたちは、自分の好きな遊びや活動に没頭している時間が長いことがよくあります。この「自分の世界」に大人が「お邪魔」するように関わることで、コミュニケーションのきっかけを作ることができます。たとえば、その子がブロック遊びに夢中なら、一緒にブロックを並べたり、積んだりするだけでなく、「このブロックは赤いね」などの声掛けをして、子どもの反応を引き出すことがポイントです。
少しずつ関わる時間を増やす
最初から長時間関わりすぎると、子どもにとって負担となり、逆効果になる場合があります。まずは短い時間から始め、少しずつ関わる時間を増やしていくのが効果的です。子どもが「楽しい」「また一緒に遊びたい」と思えるような関わり方を意識しましょう。
共感を育てる
子どもが人と共感することに喜びを感じると、言葉が出やすくなるとされています。たとえば、子どもが嬉しそうにしている場面では、「楽しいね」「すごいね」と気持ちに寄り添う言葉をかけてあげることで、共感の感覚を育むことができます。
発達が気になる子どもに対する超早期療育プログラムは、こうした取り組みを具体化するための参考になります。親が日常生活の中でできることを学ぶための本やプログラムを活用することで、無理なく子どもの発達を支えることが可能です。
さらに、言葉が出ない段階であっても、非言語的なコミュニケーション(視線、指差し、ジェスチャー)を意識的に引き出す工夫をすることも重要です。例えば、子どもが指差しをした際にその対象について話したり、ジェスチャーを褒めたりすることで、コミュニケーションに対する自信を育むことができます。
思春期にも活用できるアプローチ
この「関わり方」の考え方は、思春期の子どもたちに対しても有効です。たとえば、YouTubeなどに夢中になっている子どもに対して、ただその時間を取り上げたり制限したりするのではなく、その世界に入り込むような姿勢を見せることで、子どもの信頼を得ることができます。興味を共有する中で対話が生まれやすくなり、深いコミュニケーションへとつながることが多いのです。
子どもの言葉の発達に心配を抱える親御さんにとって、焦りや不安は避けられないものです。しかし、適切な関わり方を工夫し、子どものペースを尊重しながら進めることで、言葉やコミュニケーションの発達を支えることができます。親子の絆を深めながら、その子が持つ可能性を引き出す手伝いをしていきましょう。
-

- 保田典子
筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。
