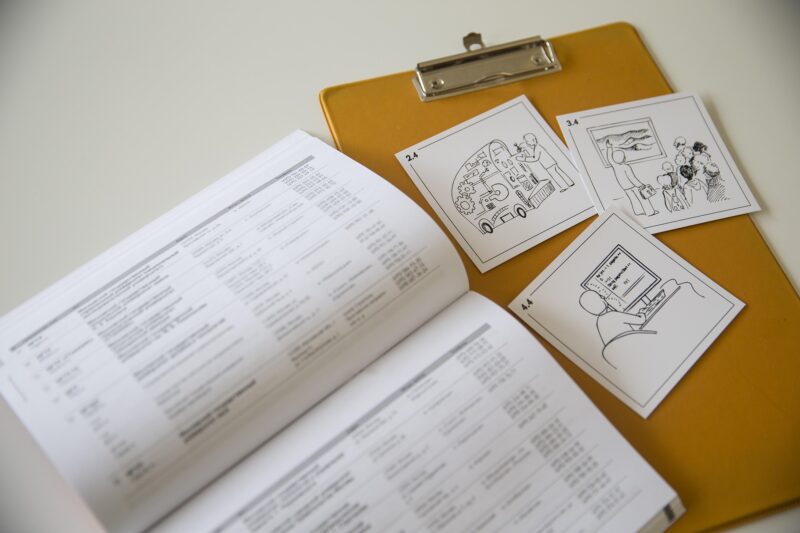
幼稚園や保育園の頃は、先生から子どもの様子を直接聞く機会が多くありました。でも小学校に上がると、学校での様子が見えづらくなったと感じる方も多いのではないでしょうか。子どもからの話や、友達・その保護者とのやりとりを通じて、断片的な情報をつなぎ合わせながらなんとなく様子を想像している。そんな保護者もいるかもしれません。
そんな「ちょっと心配だな」と思った時や第三者の意見がほしいと感じた時に、心強い存在になるのがスクールカウンセラーです。
「カウンセラーって、問題のある子が利用するもの?」
「うちの子は不登校だけど、関係あるの?」
「親だけでも相談していいの?」
そんな疑問を持つ方にこそスクールカウンセラーの役割と可能性を知っていただきたいと思います。
COCOLOプランが後押しする、日常的な「心の支援」
文部科学省は2023年「児童生徒の自殺予防に向けた取組の強化~COCOLOプラン~」を発表しました。同プランでは、子どもたちの心の安全を守るため、以下のような支援体制を強化しています。
- すべての中学校区に「心の支援チーム」を配置
- スクールカウンセラーの常勤化や配置拡大
- 学校・家庭・地域の連携強化
- 保護者や子どもが気軽に相談できる環境づくり
これら支援体制により、スクールカウンセラーは「特別な問題に対応する人」から「子どもと親の心に寄り添う存在」へと印象を変えつつあります。
例えば東京都では、1995年に一部の中学校から始まった配置が、今ではほぼすべての公立学校に広がっています。地域差はありますが週1日以上在籍している学校が多いです。 また学校だけでなく、教員経験者やカウンセラー資格をもつ方が自治体の教育センターなどに常駐し相談を受け付けています。
不登校でも相談可能。親だけでも大丈夫
お子さんが学校に通っていない場合でも、保護者だけでスクールカウンセラーに相談することは可能です。 また必要に応じて、医療・福祉・発達支援機関への橋渡しするスタートラインにもなります。
まずは「話を聞いてもらう」「家庭での様子を整理してみる」ことから始めることで、不安が軽くなるかもしれません。
私の住む自治体では、学校に設置されているカウンセリングルームの利用案内や教育相談センターのイベント告知がこの1〜2年で大きく増えました。いきなり個別相談はハードルが高いという場合は、イベントに参加して雰囲気を感じるところから始めてみるのもよいと思います。
初めは緊張するかもしれませんが、どんなにまとまりのない話でもしっかり耳を傾けてくれる安心感があります。それだけでも、自分を少し客観視するきっかけになるはずです。
保護者との連携が大事
私自身の経験でも、スクールカウンセラーの関わり方は多様です。例えば、次のような関わりが見られました。
- 「反応速度を高める練習」としてカードゲームを活用
- 子どもと「今どのくらい困っているか」を言語化(数値化)するサポート
- 困りごとがあるかどうかを、一緒に探っていく時間の持ち方
- あえて言語化せず、「ただそこにいる」ことを大切にする関わり
こうしたアプローチは、子どもの状態や気質を見立てたうえで行われます。だからこそ「今の支援はどんな意図があるのか」を保護者も理解しておくことで、家庭での関わりにも一貫性が生まれます。スクールカウンセラーとは、ぜひ定期的に会話を重ねておきたいところです。
学校での支援と、家庭での関わり方がちぐはぐになってしまうと、かえって子どもに混乱を招くこともあります。しかし、親が支援の方向性を共有しできる範囲で併走することで、子どもにとって「安心して頼れる場所」が増えます。
「変化に気づいたら、カウンセラーと共有する」「不安や疑問があれば、親自身も相談する」などのアクションを心がけると連携が取りやすいと思います。
迷っているなら、まず「親だけで」相談を
スクールカウンセラーに相談することは、「子どもに問題がある」ことを意味するわけではありません。むしろ、「親としてどう関わればよいか悩んでいる」その気持ちに応えてくれる存在です。
カウンセラーは子どもを取り巻く環境や見えにくい気持ちを一緒に整理し、言葉にしていくパートナーです。家庭内で抱え込まず子育てをチームで進めていくうえで、スクールカウンセラーはとても心強い存在になってくれるでしょう。
特に夏休み明けは生活リズムが変わりやすく、子どもの様子がいつもと違うと感じることもあるかもしれません。そんなとき、親自身が「どう関わればよいか分からない」と感じるなら、そしてそれが続くようなら、困ったときの選択肢としてスクールカウンセラーの存在を心の片隅に留めておいてください。
-

- 佐藤けいこ
会社員として働きながら、二児の母として子育て中。大学では生活科学(生理学領域)を学び、現在は通信制大学で心理学を専攻。2025年夏に卒業予定。自身の不調や子どもの行き渋りをきっかけに、「支援と家庭のつながり」に関心を持ち、家庭での関わりと心理学の理論をつなげる実践と探究を重ねている。理論と実体験の両面から、子育てや学びについて考える記事を発信している。
