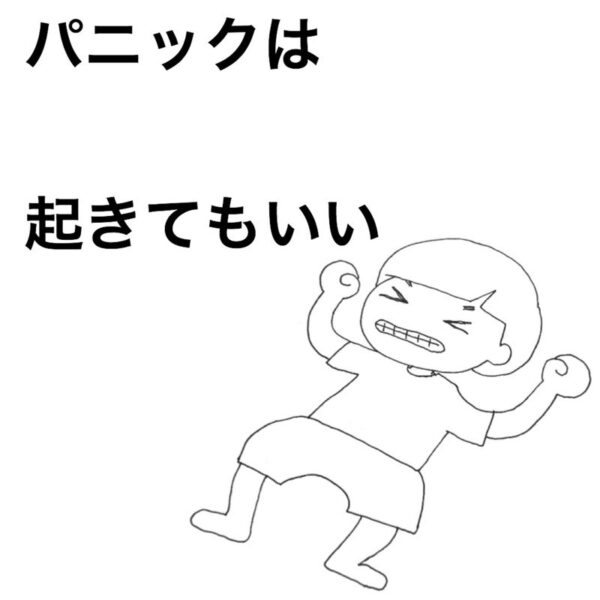
こだわりの強さから日々パニックが起こり、親も子も疲れてしまう――こうした状況に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。かつての私は、パニックを起こさないようにしてあげることが最善だと思っていました。けれども、今では少し考え方が変わり、「まあ、こんな日もあるよね!」と、自分も子どもも責めない姿勢を心がけるようになりました。
むしろ小さいうちにパニックが起きることで、その原因を洗い出し、将来社会に出たときに困らないように備えることが大切だと気づいたのです。
パニックの原因を探る際には、なるべく原因を「一般化」して考えるようにしています。その子どもが親から自立した後、さまざまな場面で柔軟に対応できるようにするためです。例えば、特定の音や環境に過敏でパニックを起こす場合、どのような条件が問題となっているのかを分析し、それがどのような状況で共通して起こるのかを整理します。
次にその原因に対処する方法を考えることが重要です。子どもが自分で解決できる方法を見つけてあげるのが理想ですが、難しい場合は、原因となる状況を自分で回避できる術を教えることも必要です。たとえば、大きな音が苦手なら耳栓やヘッドホンを準備したり、混雑が苦手なら人混みを避けるルートを考えるなどです。
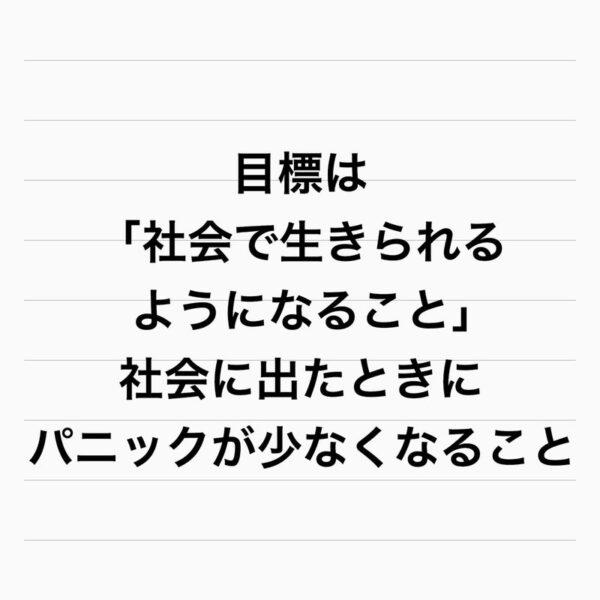
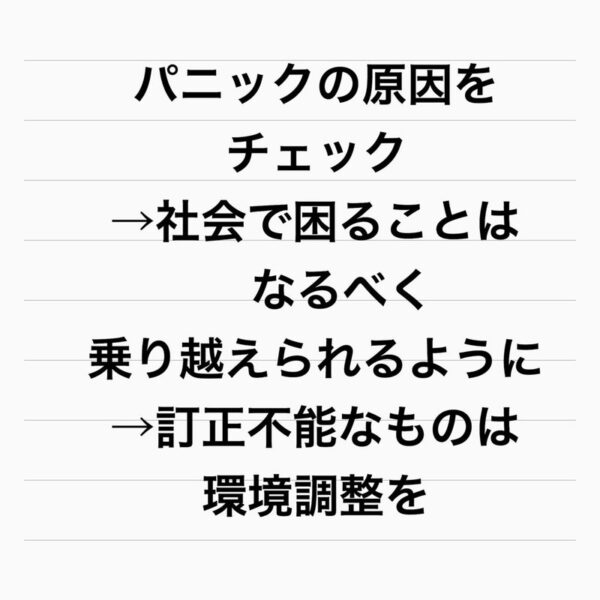
パニックが起きるたびに疲れるのは事実です。しかし、その疲労は「原因を探るための大切な機会」として捉えることで、前向きな気持ちを持つようにしています。そして、「子どもが困難に立ち向かう力を育むプロセス」と考えると、少し気持ちが楽になります。
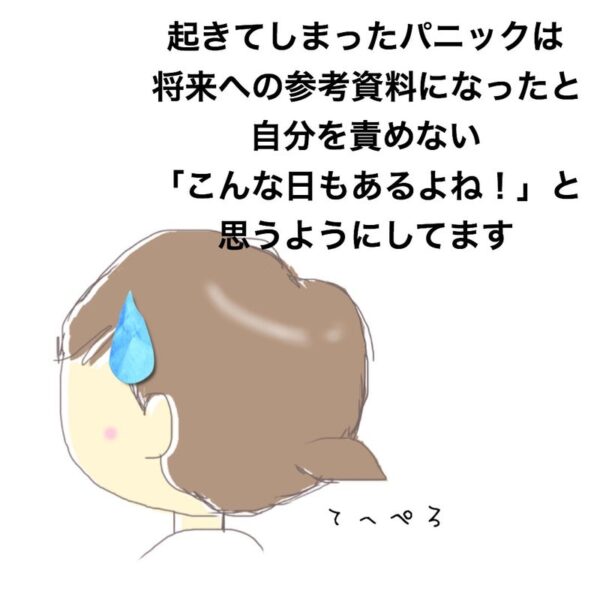
日々のパニックに向き合うのは簡単ではありませんが、親子で協力しながら解決策を見つけるプロセスは、きっと子どもが将来自立して生きていくための力となるはずです。「まあいいよね!」の気持ちで、肩の力を抜いて一緒に進んでいければと思っています。
-

- 保田典子
筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。
