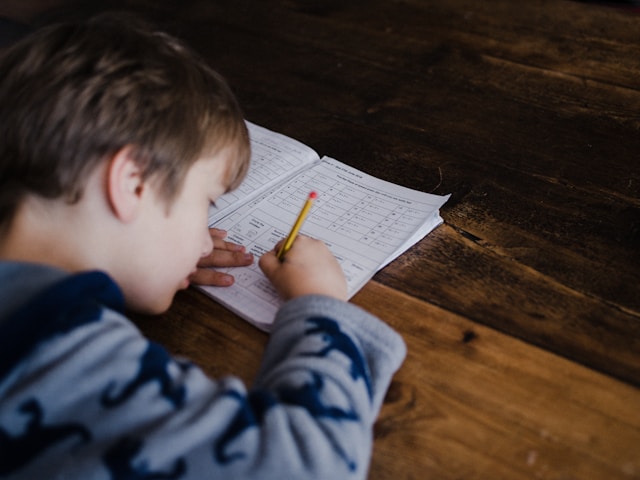
毎日のように「やることやったの?」「宿題は終わった?」と聞いているうちに、ふと気づくと疲れ切ってしまっている…そんな経験はありませんか。
最初は「やるべきことをやってほしい」という思いから始まった声かけが、いつの間にか義務感とイライラに変わり、親子の会話は“確認”と“指示”ばかりになってしまう。そんな状態では、お互いの関係性もギクシャクしてしまいます。
この記事では、まず「親の役割の見直し」という視点から、この疲れのループをほどく方法を考えます。ただし、役割を見直すだけでは問題は解決しません。子どもが自主的に取り組むようになるためには、関係性を改善し、前向きなコミュニケーションを回復させることも必要です。
小学校低学年までは、提出物や宿題の管理はほぼ「親の役割」として求められます。幼稚園時代から続く“提出物マネジメント”の延長で、宿題も「親の責任」と感じやすくなるのです。
提出が難しい状況でも、「提出期限を守らせる」ことを優先し、他の調整方法をあまり取らないケースもあります。その結果、子ども本人のためというより「親のための宿題」という構図ができあがってしまいます。
親の役割を見直すーエゴグラムからのヒント
東大式エゴグラムは、エリック・バーンの「交流分析」という理論をもとにした心理検査です。私たちの心理状態や行動傾向を5つの自我状態に分類し、その強弱のパターンから、自分の行動のクセや人との関わり方を知ることができます。その5つとは次の通りです。
- 批判的な親(CP: Critical Parent)
- 養育的な親(NP: Nurturing Parent)
- 大人(A: Adult)
- 自由な子ども(FC: Free Child)
- 順応した子ども(AC: Adapted Child)
責任感が強く、秩序やルールを守るよう厳しく求める
例:「ちゃんとやらないとダメでしょ」「時間を守らないのはよくないよ」
思いやりがあり、優しく、支援的・受容的
例:「ここまでやれたんだね、えらいね」「疲れてるみたいだから、今日はここまでにしようか」
冷静沈着で、事実や情報に基づいて判断する
感情を隠さず、本能のままに行動する。天真爛漫
感情を抑え、親や上司の顔色を見ながら、そのいうままに行動する
「CP」が強くなりすぎると、指示や命令が増えてしまいます。一方で「NP」が少なすぎると、子どもは支配的に感じやすく、従順になるか反発するかのどちらかに傾きやすくなります。
特に、仕事でリーダーや管理職などの役割を担っている場合、職場で求められる「CPモード」のまま家庭に戻り、無意識に厳格な態度を取ってしまうこともあるでしょう。
仕事モードから家庭モードへの切り替えは、意識して行う必要があります。もし今の自分が「CP」に偏っていて息苦しさを感じるなら、意識的に「NP」の行動を増やすことでバランスを取り戻せるでしょう。
エゴグラムのようなツールは、この「バランス」を客観的に把握する助けになります。
自主性を育てるための土台としてー関係性とコミュニケーション
役割のバランスを整えただけでは、子どもの自主性は十分に育ちません。自主性を支える土台は、信頼関係とコミュニケーションです。
- できていることを見つけて言葉にする
- 期限や量を柔軟に調整する
- 部分的なゴール設定をする
-

- 佐藤けいこ
「まだやってない」より「ここまでやれたね」を優先
遅れそうなときは先生に相談し、部分的な提出や期限延長を試みる
「全部やる」ではなく「これだけやってみよう」にする
そして何より、「やらせる」から「一緒に考える」へ。親が横に並んでくれる感覚は、子どもが自分のペースで挑戦するための土台になります。
「やることやったの?」が増えすぎて関係が悪化していると感じたら、まずは自分の中の“親の役割”を客観的に見直してみましょう。エゴグラムなどの簡易診断はネットでも手軽にできます。セルフチェックページ例もあるのでご参考ください。
親の役割を整え、コミュニケーションを深めていくと、「やらせなきゃ」という負担は軽くなり、子どもが自分の力で進んでいく瞬間が垣間見えるようになるでしょう。
■参考文献
津田太愚(2004) 『新・エゴグラム入門』イースト・プレス
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
会社員として働きながら、二児の母として子育て中。大学では生活科学(生理学領域)を学び、現在は通信制大学で心理学を専攻。2025年夏に卒業予定。自身の不調や子どもの行き渋りをきっかけに、「支援と家庭のつながり」に関心を持ち、家庭での関わりと心理学の理論をつなげる実践と探究を重ねている。理論と実体験の両面から、子育てや学びについて考える記事を発信している。
