
米国の公共政策研究および非営利教育組織であるIndependent Instituteが、Brian Baugus氏の著書『ホームスクーリングの経済理論』についてレビューを掲載しました。その内容を抜粋してお伝えします。
同書は米国におけるホームスクーリングを、斬新かつタイムリーに分析した書籍です。ホームスクーリングの歴史的概観から始まり、公立学校への不満が高まるなかで、ホームスクーリングが現実的な教育的選択肢として台頭してきた経緯を考察しています。
バウガス氏は、標準化されたK-12教育(米国における幼稚園から高校までの13年間の教育期間)の硬直的な構造は、米国の家族の多様な価値観やニーズに対応できず、ホームスクーリングに関心が高まる土壌を作り出していると主張しています。
本書の中心的な主張は、官僚主義的な制約と画一的なアプローチに縛られた公立学校制度は、政治的・宗教的に多様な人々の多様なニーズを満たすには不十分であるという点です。公立学校が個々の学習ニーズに対応できないことが、親たちをホームスクーリングへと駆り立てるとともに、子供たちの個々の興味・適性に合わせた教育体験がカスタマイズされる背景としています。
著名な思想家たちの事例を、ホームスクーリングの分析に用いている点も同書の魅力です。彼は起業家精神と市場ダイナミクスの概念を援用。ホームスクーリングが分散型かつ多中心型の枠組みの中でどのように機能するかを解説しています。
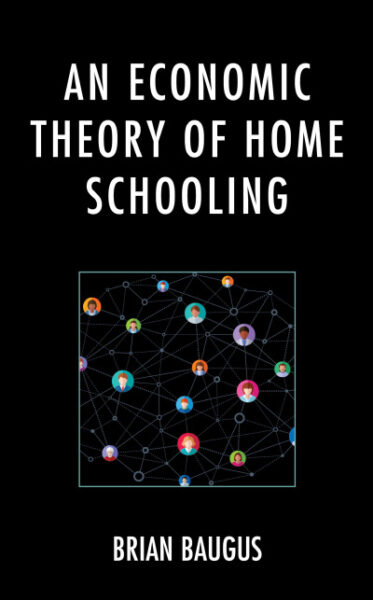
公立学校の中央集権的な官僚主義は革新性と対応力を阻害する可能性がありますが、ホームスクーリングは保護者、教育者、そして地域社会の間で協力関係を築くネットワークを育みます。この分散型の構造により家庭は協同組合や非公式な学習グループを形成し、学問分野からスポーツや芸術といった課外活動まで、多様な教育機会を提供することができます。
なかでも起業家精神理論の応用は、特に興味深いとレビュワーを指摘しています。バウガス氏は、シュンペーターの「創造的破壊」、カーズナーの「アラートネス」、ボウモルの「ラディカル・イノベーション」など、さまざま起業家精神のモデルを提示。ホームスクーラーがどのように起業家としての役割を担ってきたかについても解説しています。
多くのホームスクーラーは、子供たちをより良く教育する機会に敏感でありながら、新たな機会が訪れた際にそれを捉える柔軟性も備えており、それはカーズナーのアラートネスのモデルに当てはまります。また一部のホームスクーラーは創造的破壊に関与しています。というのも、標準的な教育における欠落部分を親が補うためにカリキュラムや教育法の市場が新たに生まれているからです。
一方、本書はホームスクーリングを取り巻く誤解のいくつかを払拭しています。バウガス氏は、「ホームスクーリングは子どもの社会化を促進しない」という一般的な批判に対し、実際には活発な社会的ネットワークが構築されることが多いと実証し反論しています。これらネットワークは、学業だけでなく、豊かな社会的交流や協働学習体験を促進するものです。ホームスクーリングを行う家庭は、地域リソースを活用することで、従来の学校教育で得られる社会的機会を凌駕する教育環境を作り出しているとバウガス氏は指摘します。
ホームスクーリングの「革新性」と「柔軟性」を探求している点でも同書は評価されています。著書は標準化されたカリキュラムが存在しないことで、親は教育方法を試行錯誤することができ、学習における創造性と個別化を育むことができると主張しています。この柔軟性は、テクノロジーの進歩や新たなキャリアパスの出現など、教育の可能性が絶えず進化する現代において極めて重要となります。
ホームスクーリングに消極的な親たちのエピソードも参考になると、レビュワーは評しています。例えば、ある家庭の子供が「学校が学習障害に適切に対処しておらず、適切な課題にも取り組ませていない」と親を説得する様子が描かれます。それまでホームスクーリングはしないと誓っていた母親も、子供の苦闘が深刻化していくのを見て考えを変えました。同時にホームスクーリングによって、公立学校に通っていた時よりも幅広い読書や学習を行えるようになったことにも気づきました。
なお同書は複雑かつ抽象的な議論が多く、注意深く読まなければ解釈が難しい場合もあるそうです。経済概念に馴染みのない読者にとっては、少し苦労する読み物となりそうです。ただレビュワーは『ホームスクーリングの経済理論』が、ホームスクーリングという現象について示唆に富む考察、そして同教育を選択する根底にある経済的・社会的ダイナミクスへの貴重な洞察を提供していると評価しています。そして教育者、政策立案者、保護者にとって一読の価値ある一冊であると締めくくっています。
(EDICURIA編集部)
