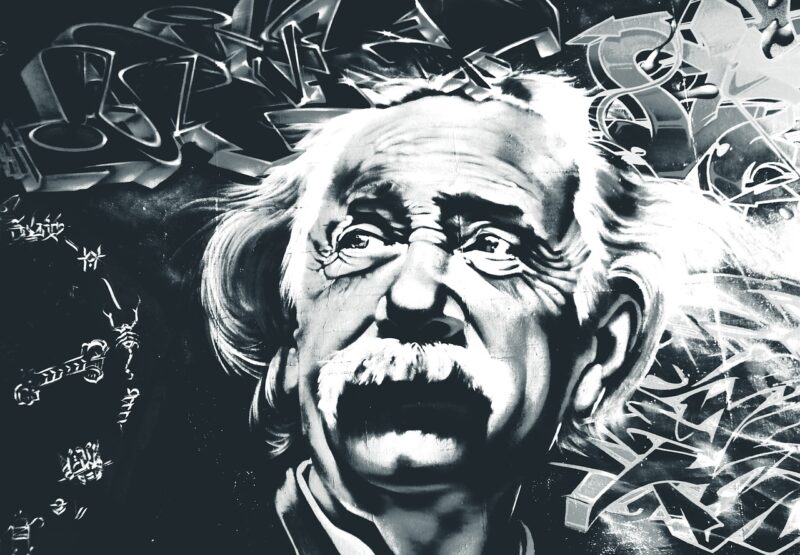
世の中には知育に関する本やグッズが溢れていますね。生まれてすぐに通える幼児教室もたくさんあります。早期の幼児教育については、小児科医師の中でも意見が別れます。私個人の意見は、天才性を育てるような先取り教育に関してはあまり肯定的な考えは持っていません。
幼児教室の宣伝には「3歳までにやらないと手遅れになる」「平均IQ150以上」などの文言などが飛び交い、早期教育の必要性をうたっています。幼児教育が生まれてから少し歴史が経過したこともあり、高IQの子がその後どうなったかというデータも出てきています。
シカゴ大学ヘックマン教授らの「ペリー幼稚園プログラム」の研究によると、幼稚園時代にIQが高かった子どもも、8-10歳になるとその効果はなくなってしまうというそうです。
IQは「同年代に比べて現在どのくらい認知能力があるかという相対評価」です。早期教育をすると「短期間、認知能力は上がるものの効果は長続きしない」ということでした。またIQの効果は短期的だけれど「非認知能力を伸ばすことで将来の学力や所得が良くなる傾向がある」とも結論づけています。
人間は発達する生き物です。先取り教育をしても放っておいても、段階的に子どもたちは発達します。焦らず成長を見守り、時に適切なサポートをすることで、子どもは能力を獲得していきます。
発達障害と早期療育の関係性
他方、言葉が遅いなど発達障害を疑われるお子さんに対しては、早期療育の効果が高いということも分かってきています。そのため、1歳半健診で早期に発達障害の疑いのある子を見つけてあげて、早期療育につなげてあげようという取り組みが小児科の中では重要にもなってきています。
なお上のきょうだいがいる子の方が発達が早い傾向があるように、子ども同士の相互作用によって発達をうながすことができます。
近年、愛着障害などの研究から、夫婦げんかが多い・DVがある・体罰を受けている子どもは、そうでない子どもに比べて脳の一部が萎縮したり、不安定で情動的な行動をとる(例えば精神的に不安定になったり、暴力的になる)ことが多くなることが分かっています。子どもの行動や情動が不安定になることにより、成績や精神的な安定に影響が出ることも考えられます。
ひとり親はよくない、まったくケンカしない方が良いという話ではなく、子どもが安心して過ごせる家庭を作ることが子どもの安定に繋がり、その教育を効果的にすることができます。夫婦げんかであれば、きちんと夫婦で「ごめんね」と言い合ったり、ギスギスした雰囲気を引きずらないなど、ケンカをしてしまったあとにどう振る舞うかが大事です。
子どもの発達をうながす大事なポイント
1-3歳の子どもの発達をうながすために、大事にしたいポイントがあります。
まずは「ライフスキルを身につけること」です。排泄(おしっこやうんち)、食事、睡眠などをきちんとするということです。1歳でおむつを外さなくてはいけない、というわけではもちろんなくて、トイレを自分で表現できるようにする方法を少しずつ声かけしていく、ということからでも大丈夫です。規則正しく食事をして、睡眠がしっかりとれていると、子どもの情緒が安定して、成長にも繋がります。
次に「言葉のトレーニングをすること」です。言葉が使いこなせるようになると、自分の気持ちや表現したいことが他人に伝えられるようになります。言葉が知能の第一歩になるのです。実際にしゃべる言葉が出なくても、自分の表現したいことができるようになってくる、というだけでも子どもの情緒の安定と成長につながります。言葉の発達が心配であれば、かかりつけの小児科医などにご相談ください。
興味のないフラッシュカードを機械的に見せたり、やりたくないことを無理やりやることは子どものためにもなりません。子どもも親も楽しく教育ができて、安定した家庭環境で知育をすることができれば、すごく効果的な教育になると思います。具体的な知育をする暇がなかなかなくても、日々の声かけを工夫したり、有効なほめ方をするだけでも知育とも言えるでしょう。
-

- 保田典子
筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。
