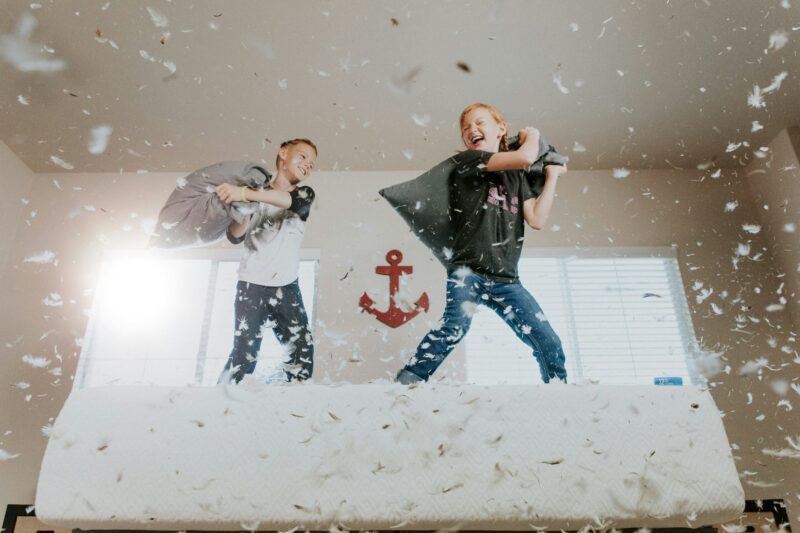
子どもは結構ぐずることが多いですよね。特に赤ちゃんの時期は「ぐずる」というよりも泣くことが多いですが、イヤイヤ期になるとぐずぐず度が増します。それが終わったかと思っても、気に入らないことがあるとまたぐずぐずする。では、なぜ子どもがぐずぐずしやすいのかというと、その原因の一つとして、感情表現を他の方法で伝える術を知らないからだと言われています。実際、ぐずぐずだけではなく、噛みつきなどもその一環です。感情に関しても、どう表現して良いか分からずにフリーズしてしまうのは大人でも同じです。
学校や習い事では感情表現を教えてくれません。悲しい時に泣く、怒っている時に訴える、楽しい時に笑い声を上げる。これらは、感情表現として非常に大切なものです。しかし、実際に学校の先生たちが感情を表現することは少ないですよね。普段、先生が感情を露わにしている姿を見かけることはほとんどありません。
では、ぐずぐずせずに自分の気持ちを表現する方法をどこで学ぶのかというと、やはり親から学ぶことが多いのです。特に母親からです。「もっとママも感情表現を!」というのが私の考えです。日本の母親たちは非常にしっかりしていて、子どもの前でいつもちゃんとしている姿を見せていることが多いですが、これが実は子どもにとっては感情表現を学ぶ機会を奪うことになりかねません。
私自身、半年ほど前に父が病床にあり、精神的に不安定な時期がありました。その時、子どもが言うことを聞かないと私は泣きまくってしまいました。でも、その時、私の感情を言葉で表現するようにしていました。
「歯磨きをしてくれなくて、虫歯になるかもしれないのが心配だよ」
「おじいちゃんが具合が悪くて悲しい」
そういった感情を言葉で伝えたのです。その結果、子どもが「ママ、悲しい?」と聞いてくれるようになり、感情の理解が深まっていきました。だから、母親たちにはもっと感情を表現してほしいと思っています。楽しいときに大きな声で笑ったり、辛いときに泣いたり、悲しいときには何もしたくない気分になっても、それを自然に見せていいのです。
子どもが感情を理解する過程では、まだ自分の気持ちをうまく表現できない時期が続きます。そのため、ママが子どもが泣いたりぐずったりしたときに、その感情をどう受け止めて解釈して伝えるかが大切です。「おもちゃを取られて悲しかったんだね」とか「嫌いなご飯が出て困ったんだね」などと声をかけてあげると、子どもは自分の感情を少しずつ理解し始めます。間違っていたとしても大丈夫です。その後、子どもは自分なりに表現方法を学び修正していくことができます。
今の段階では、子どもに伝える表現方法をできるだけ豊かにしてあげることが大切です。また、感情を表現することと同時に、理由を伝えるときにはなるべく冷静に落ち着いて伝えることが望ましいと思います。
-

- 保田典子
筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。
