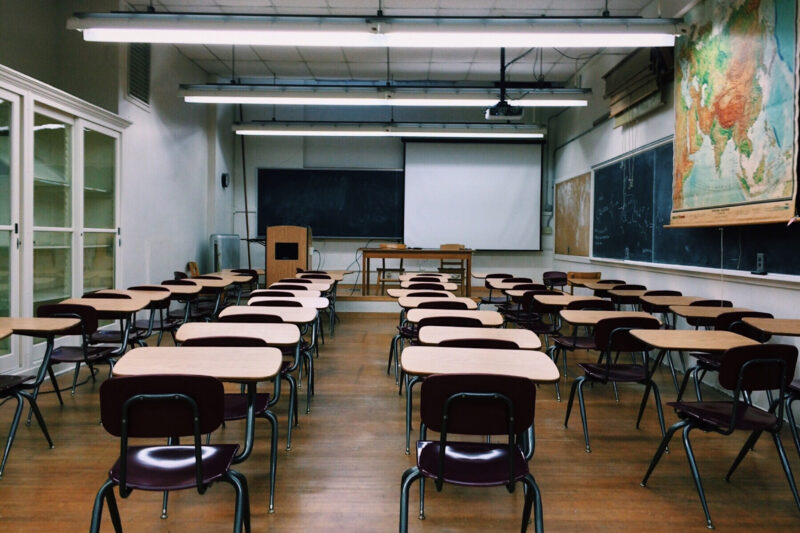
日本の児童の不登数は年々増加しており、2024年度の小中学生の不登校は34万6,482人、高校生は6万8,770人といずれも過去最多を記録した。背景には人間関係や学習のつまずきなどさまざまな要因があるが、「家庭の所得」も登校状況に大きく影響しているとされている。例えば、国内の調査では世帯年収200万円未満の家庭では不登校の割合がもっとも高く、600万円以上ではリスクが大幅に低下するとされている。
では家庭の所得が上がれば不登校は解決するのだろうか。日本国内には直接的な因果関係を示した統計やデータは見当たらないものの、海外では一定の効果があるという分析が示されている。
例えば、メキシコの「プロスペラ」(Prospera)という条件付き現金給付制度(Conditional Cash Transfers=CCT)では、貧困世帯に対して子どもが学校に通うことを条件に現金を支給。結果として、中等教育の在学率が男子で約10%、女子で約20%上昇したと報告されている。またブラジルの「ボルサ・ファミリア」でも同様で、プログラムに参加した家庭の子どもは中退率が7.6%低下し、出席率も改善したとされる。
アメリカの研究も示唆的だ。デラ&ロクナー(Dahl & Lochner)の研究では、低所得層の労働意欲を高め貧困解消に資するために、一定の所得までは勤労所得に一種の補助金を与える制度「EITC」(Earned Income Tax Credit)を実施した結果、わずか1,000ドルの所得増が、算数・読解力の標準偏差で3%のテストスコア向上に相当し、特に教育機会に恵まれない子どもに効果が強く見られたと報告している。またEITCによって、大学卒業率が4.2%、就労率が1.0%、成人期収入が2.2%増加したとする報告もある。「所得の向上が登校や学びを後押しする」という因果関係は数カ国で裏づけられているようだ。
ただし注意点もある。というのも、これらの政策が改善を後押ししたのは主に「出席率」や「進学率」だ。日本の主な不登校理由である「心理的な抵抗による長期欠席」の改善を直接示すものではない。安定した経済的基盤は前提や必要条件のひとつであり、人間関係や学校への不安は別の課題として残るということになりそうだ。
(EDICURIA編集部)
